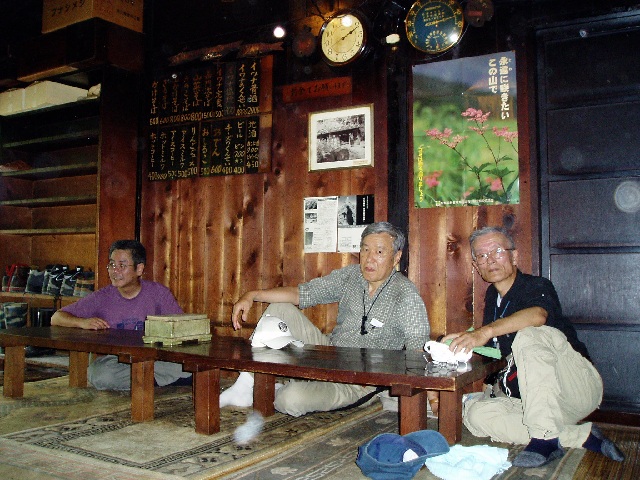02
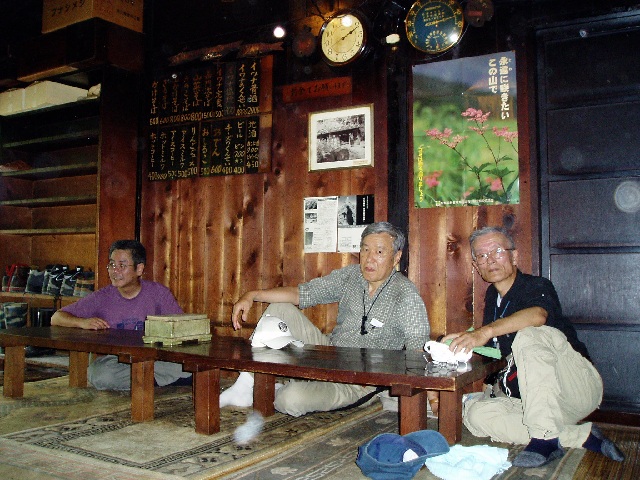
03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

大学時代の友人の愛甲氏に誘われ、8月4日〜7日の上高地への山行に加えていただきました。
私は、
41年間の会社員生活をこの6月に卒業し、いまだ新しい生活のリズムを模索していたところです。山へは学生時代に多少親しんでいて、リタイヤしたら、ただ漠然としてですが山や、自然の中を逍遥したいと思っていました。昔のザックや寝袋を引っ張り出し、約40年ぶりの重さにふらふらしながら出かけました。最近丹沢や、奥多摩の低山を3回登ったりしていましたが、足にはまだ自信がありませんでした。愛甲氏、吉川氏、稲葉氏にお供して、なんとか徳沢園に到達しました。
翌5日、稲葉さんの推奨もあり、槍ヶ岳へ向かうお二人(愛甲・稲葉氏)を見送り、私は徳本峠を目指しました。徳本峠は、島々から上高地に入る古道である事は昔本で読み知っていましたし、串田孫一の随想なども読んで峠には一度立ってみたいとあこがれていました。
徳沢を出て、7時5分に徳本峠への分岐に入りました。分岐には島々への道の通行止めを知らせる看板が立ててあります。樹林の中、車が通れるほどの平坦な道を大瑠璃のさえずりを聞きながらたどると、道は細くなり沢沿いに上っていきます。迷う事もなく、あえぎながら、小休止をしながら登っていきます、多少悪い個所もありますがほぼ歩きやすい道です。休憩している山小屋の人と思われる二人をやり過ごし、もう降りてくる、二組の家族連れと挨拶を交わし、岳樺や落葉松の樹林が早く切れないかと、苦しい息をしながら時々上のほうをのぞきます。やっと9時30分に峠に飛び出ました。
峠からは明神岳と穂高の鋭鋒が眼前にあります、峠より霞沢岳の方へ少し上ったところがビューポイントです。島々側に、昔ながらの山小屋らしい徳本小屋が建っています、その前から八ヶ岳連峰が雲の上はるかに浮かんでいました。
私は、峠で写真を取り、ビューポイントでスケッチを2枚描いたりしてしばらく楽しみました。勇躍峠を降り、明神から梓川の右岸を歩き河童橋に向かいました。時間が有り、河童橋をスケッチしようと思ったのです。しかし、人が多いのと暑さであきらめ、腹も減ってきたのでバス停傍の食堂で食事にしました。
夜は大きなテントで、吉川氏と2人だけです。取り留めのない話を交わし、少し酒を飲み、久し振りの寝袋に入りました(昔の寝袋で、多分2キロぐらいあります)。
6日は吉川さんに相談し、徳沢に登山口がある長塀山(
2,564m)に向かいました。吉川さんからは、欲を出して蝶が岳には足を伸ばさないよう注意され、3時の帰着を約束し6時30分に出発です。いきなりのきつい登りです。木の根、岩角に掴まりなまった体を引き上げていきます。私と同時に2人組みが入りましたが、当然どんどん離されてすぐに見えなくなります。そのうち降りてくる人が増えてきました。20人以上のツアー登山者をやり過ごします。苦しいので小休止をかね道を譲りますが、かなりのロスタイムです。樹林越しに穂高の山がチラチラ見えます。少し平坦なところに出たと思うと又直登です。いかにも頂上手前かと思わせる道を急ぎますが急登が尽きません。いいかげん嫌になり、困憊したところで樹林に囲まれた頂上です。木の間越に穂高の方が見えますが、苦労した代償としては面白くもない狭い頂上で、三角点がちょこんと有り、粗末な板に長塀山とあります。
10時到着でした。徳沢でキャンプしていた小千谷高校の
Partyが美味そうなサンドイッチを頬張っています。三角点の写真を取り、ゆっくり休息し、食事にします。登ってきた登山者と見晴らしのなさを話していたら、20分も進めば見晴らしの良い所へ出るといいます。ガイドブックにはそんな記述はありませんが、20分なら行って見ようと踏み出しました。上り下りを繰り返し、お花畑や小さな池が出てきますが、見晴らしの良い所には20分経っても出ません。仕方なく、12時になったら戻ろうと決心し先に進みました。突然樹林が消え、
残雪の残る池と這い松の丘が見えるところに出た時は、一瞬すべてを忘れました。這い松の中を進み、蝶ヶ岳ヒュッテの赤い屋根が見えてきました。ガレた稜線を進み、槍ヶ岳のそれと分かる穂先が見えます。私は覚えず、蝶ヶ岳へ来てしまいました。常念岳に向かう所の見晴台で槍をバックに写真を取ってもらい、蝶ヶ岳頂上に向かいそこでも写真を取ってもらい、あわただしく帰路につきます。12時15分でした。徳沢には2時間40分で降り、3時帰着の約束に間に合いました。
夜は宮本さん、鶴留さん、伊井氏が合流され賑やかに食事し、満天の星を久し振りに見ました。
この4日間は私にとって、忘れていた自然への感動をもたらしてくれ、忘れられない日々になりました。この機会をいただいた皆さんに感謝いたします。
特に吉川さんは食事や登山の的確なアドバイスをいただきありがとうございました。よろしければ、又のお誘いをお待ちします。
猿渡生祥 記