富士高校山岳部40周年にあたって
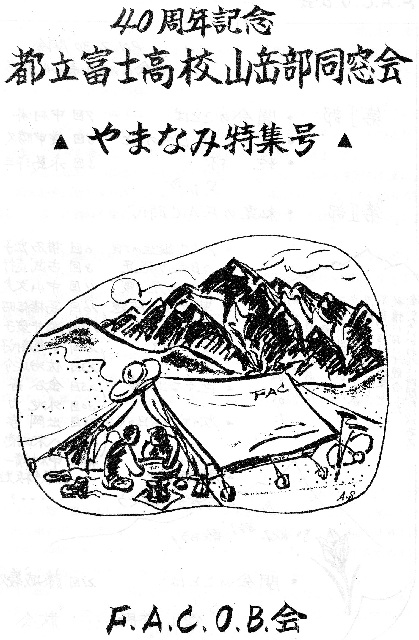

発起人代表
第13回 愛甲 勝久
昭和33年より昭和40年春迄、私は高校、大学の7年間を、FACの部室で過ごしました。その間多くの先輩後輩とめくり逢い、その人々は私の人生のかけがえのない宝となっています。W.ホイットマンの詩に
Passing Stranger you don’t know how longinlgy I look up you!という一節があります。共に山で過ごした日々、今は会うことの叶わぬ旧友も、そのひとりひとりの思い出を携えて日々を過ごし、私は今日までの50年の人生を歩んできました。
今を去る10年前、当時OB会で精力的活動をしていた18回生の赤羽創君の発案によりFAC30周年記念の集りを計画したことがあります。また同時にFACの30年を顧みる記念誌を創るべく多くの資料を集めました。残念乍らその試みは様々な理由により実現しませんでした。
以来OB会の組織的活動は休眠状態となったのでしたが、幸いにも、大学生が現役をサポートする伝統は今日に至る迄引き継がれた為、ここに40周年の集りを実現出来る事になった訳です。今回の準備の過程で、FACのルーツ、つまり発足時のメンバーである第5回生永島先輩のご出席を得、FACの全史を展望する事が出来たのです。当日出席の仲間達、次回の出席を期し熱いメッセージを御返信下さった皆さん、本当にありがとう。
当日の様子をささやかな冊子にしてお送りしますので、これからも是非この集まりへ御支援の程、よろしくお願い致します。
終わりに私事ですが、私が再び逢う事の出来ない旧友藤原彰夫君へ報告致します。君が逝ってしまった事が無念であったと。
開会のあいさつ
第7回 中村(花岡) 昇
大変な人数で驚きました。本日はお忙しい所多数御参加下さいまして、発起人の一人として厚く御礼申し上げます。FACも40周年を迎えて、昭和28年に第一回の卒業生以来およそ250名の仲間が巣立っているとの事です。本日77名の仲間と小泉先生を始め7名の顧問の先生を迎え、盛大なFACの総会を開く事が出来、心から喜んでおります。
私は55歳になり、この5月に孫も生まれおじいちゃんになりました。FACも40周年という事でお互い40歳のひらきがある訳です。とはいえ同窓の山の仲間ですから今日は年代を越えてざっくばらんに、ご歓談お楽しみください。
昨日アルバムを何十年ぶりかで開いて見ました。私は1年生の秋に入班(当時は山岳班)して大菩薩峠に行きましたが有史以来2000メートルを越えたと話題になりました。翌2年生の夏合宿として北ア槍ヶ岳に挑戦。その秋に第 回の文化祭が開催され、山岳班も参加する事になりましたが、展示する物がなかった為、当時歌舞伎町にあった登山用具店に行き、一式借りて来て展示した事を覚えています。翌年3月には雪の谷川に春期合宿として、皆スキーを担ぎ大きな荷物を背負って、今はスキー場になっていますが、天神平にあった山小屋を2階の窓から出入りして使いました。又、槍ヶ岳の合宿のあと、「やまなみ」第一号を皆で手分けしてガリ版刷りでつくりました。
今日はこれを機会に、今後のFACの事も話題にして頂いて一層のご協力を頂きたいと思います。ありがとうございました。
創設の頃
第5回 永島 洋三
私が富士高校に入りましたのは、昭和25年1950年でございました。4月入学の年の1月から都立第五女子高校(新制1期〜4期迄)から都立富士高等学校と名前が変わりまして、私達が第一期の男子生徒として入学した訳です。従いまして私ども3年間非常にいい思いをして学園生活を送ったんです。先輩が女子ばかりでしたので山岳部というのがございませんでした。そこで私ども5、6人の有志で山に行こうということになりまして「あけび」というグループをつくりまして、これが多分後に発展し富士高山岳部になったんだろうと思います。当時中央線で新宿発23時55分鈍行で長野行きの列車がありました。これに皆で乗りまして、大菩薩とか北アルプスとか午後2時位から新宿のホームに並びまして、出掛けたことを覚えています。この鈍行の1時間位前に準急アルプスという寝台付の列車がありまして、いつか我々もあの寝台車に乗って山にいきたいと希望しつつ、富士高を卒業したわけです。
今日40年皆様の手によって発展した山岳部を、本当に嬉しいと思います。それでは乾杯しましょう。
顧問の先生方の近況
小泉千枝先生
小泉でございます。今日の(出席者)名簿では10人目位の方々から2行目の何人かの方々と一緒に山に参りました記憶がございます。70になりましたので、只今下り坂で、山に行かないのかとおっしゃいますが、山どころか地面の下の地獄のほうへむいて、そろりそろりと今歩いている所でございます。何もしておりません。
和田寛先生
私も学校を辞めてからそろそろ10年近くなります。ですから大体年齢もおわかりと思いますが、今渋谷まで来まして、ハチ公の前を通りましたが、わたしはハチ公の生きているのを見たことがある位でございますから。今家でふらふら、皆さんの働いているおかげで、年金生活しております。
西村文男先生
西村でございます。今は久し振りで懐かしい方々にお会いでき、山のことを思い出して嬉しく思っております。私は富士高から秋留台高校、荻窪、小平の並木高校、新宿と3年前に退職いたしました。只今カナダ国際大学の事務局に居りまして、雑多な仕事を全部やっております。学生(募集)の方も、もし知り合いのお子さんが居りましたら、よろしくお願いします。
新島岩男先生
新島です。富士高は25年お世話になったんですけれど、平成元年に退職しました。(出席者)名簿を見ていたら、25年の内15年間は顧問として皆さん面倒を掛けたと思いますが、非常に懐かしい人達が居りまして、今日お招きくださいまして、本当にありがとうございます。今、河合塾と東伸ハイスクールと二つこき使われております。山のほうは腰が弱くなって登っていませんけれど、倅が私に代わってロッククライマーになりまして、頑張っております。そういう訳でよろしくお願いします。
小刈米美津子先生
お久し振りでございます。私は小泉先生、和田先生の丁度金魚のフンみたいに、お二人に付いて山岳部の顧問になりましたのは、大学時代に私山岳部に属しまして山ばかり登っていた関係でそういうことになりました。22、23、24歳位まで毎月つきあって山にいっていた良き時代だったと思うんです。その後私も結婚し、出産しましてから山に足が遠のきまして40歳で富士高から国分寺高校に転勤いたしました。そのころ子供も小学校高学年でそろそろ家を空けられる様になりましたので、山岳部の顧問に返り咲きました。40を過ぎてから山をやりだしたんですが、男子ばかりの部なので最初はきつくて、肉離れを起こしました。以来ずーっと細々とやっていまして、今年は3月にヒマラヤトレッキングをやって、最近はワンダーフォーゲル部の顧問として老いをカバーしながらやっていきたいと思います。
伊藤良徳先生
伊藤です。今日はお招き下さいましてありがとうございます。私が飯豊にいきまして土田を亡くしまして、非常にショックだったんですけれど、その後何度もたてなおして、山岳部がつぶれてしまう、つぶれてしまうことになるんじゃないかと不安でしたけれども、後輩に順々に引き継がれていったことを非常に嬉しく思っています。先程も紹介されましたその時のリーダーだった萬濃もヒマラヤで亡くなってしまいましたし、実は自分が担任しました岡がサブリーダーだったんですが、彼も大学の最後の年に亡くなってしまいました。辛い思いもしましたが、その後後輩が元気に立ち直りました。その時(飯豊合宿)にもOBの方々に遺体の引き揚げ作業や何かと世話になり本当に山岳部に属していてよかったなあとしみじみ感じました。
現在は昔の教育大付属高校、今筑波大付属高校といいますけれど、富士高の時は山とサッカーをやっていましたが、向こうは山がありませんので相変わらずサッカーをやっています。私は新制の高校で14回なので愛甲さんが(FACで)一番先輩と思っていたんですが、今日はそれよりずっと古い方が沢山いらしたので、思わず下を向いてしまうといった状態です。本日はどうもありがとうございました。
谷畑先生
谷畑です。こんにちは。現在は戸山高校に移って7年目になります。生徒との山は付き合えませんので、職場の教員で山に登ることを毎年夏休みにやっております。今年も平均年齢は50歳をはるかに越えるんですけれど、14、5人で小蓮華にいきました。この頃そんなに元気ではないんですが、年寄りの山を続けたいなあと考えております。
<私達のFAC時代>
FAC誕生の頃
第6回 椎名(森田) 宏子
久し振りに皆様にお目にかかれて、脈々と富士高山岳部が続いていた事に感激しております。私が高校に入った時はもう永島洋三さんが山岳班をつくっていらして、日帰りの奥多摩などにでかけていました。それに参加させて頂いて、何人かで日帰りの山の計画したのが最初でした。何とか合宿を持ちたいということで、一番最初に計画したのが槍ヶ岳の合宿でした。そのころ顧問は数学の西村先生で、その後に木村先生が富士高に転任されて、本格的な山岳部活動が始まったと思います。昨日は学校が5日制になったと新聞で大々的に報道されていましたが、私達の高校時代は5日制でした。金曜日の晩になりますとリュックを背負って山に入り、土日と山を歩いていましたから、今更何が5日制かなあと、本当に良い時代に山を歩いたと思っています。
2年下の田中さんがヒマラヤのマカルーへでかけ、頂上に富士高のバッジを埋めてきたよと言われ感激しました。それが一番の最初の頃の思い出です。
私は未だに山に登っていますし、スキーにいらっしゃる方、また山に登る方、山を眺めたい方是非是非お使いになってください。
|
先輩のロッジは、 長野県北安曇郡白馬村北城3485−3「Hollyhock」
Tel. 0261-72-6437 Fax
0261-72-5162 娘さん御夫婦が管理されております。 |
OB会の発足
第8回 吉武 志行
皆さん今日は。40何回生迄いる中にいるなんて恐ろしいような、大変びっくりしています。私達の年というのは、先程の椎名さんやご出席の沢田さんと同期みたいな感覚で、女のほうが一大勢力を誇っており、そういう方々が中心となり山岳部の元気な時代が出来ていった訳です。木村先生が講師として来られてから、雪山や夏山も本格的登山に入っていったような気がします。高校時代の記憶で鮮烈なのは文化祭の展示の準備のため、木村先生の当時の飯田橋の下宿に毎晩のように集まり、スライド作成やらナレーションを入れる作業をしたことでした。そんなクラブの結びつきを高校卒業とともに散らばってしまうのは残念だと思い、同好会、OB会を作ろうと、新宿の喫茶店(「ケルン」だと思います)に集まり、コーヒーを飲みながら「同朋登高会」という、峰々に憧れる登高会をつくりました。その会を通じて暫くの間山登りを楽しみ、後輩の所へ指導めいたことに行ったりしていました。その様なものが基になって、今このOB会があるんだと思います。
存亡の危機
第11回 中山 文夫
実は与えられたテーマが一体どういう事かと思いましたが、私が山岳部に入りましたときは先輩が男性2人女性の方も2人か3人だったんです。当時は男子生徒が3分の1しかいないにもかかわらず34年前とはいえば、残念ながら男女同権とはいいつつも男性社会でありまして、しかも山岳班というものはリーダーは男性しかいないという固定観念がありました。私は入りました時は男性が1人、2年になりましたときに後輩に男性が1人もいない。その上私自身2年生の5月の連休に谷川岳一の倉沢で落石に遭い、夏一杯入院しておりました。こんな状況から山岳班が果たして続くかなあと不安であったわけです。幸いその後2年に男子2人が入り、3年になりまして4月にはじめて愛甲、雨宮、伊井、池田、若林、境とまとまって男子が入班し、3年の夏まで彼らを先導し、やっと一安心した訳です。
男女差の問題
第16回 高橋 信昭
実は私は今、毎日のように山に登っています。山に登るのが仕事になっていまして、夏はパラグライダー、冬はスキースクールを仕事にしています。住んでいる所は山の麓のスキー場です。思い起こしますと、あの高校時代の3年間は、先輩方からたたき込まれた山の基本と、自分のやってきた山の楽しさスキーの楽しさがそのまま原点となって、今ここに自分がいるんだなあと感慨があります。当時は田中礼三君、中井孜君、浜田弘豊君とかなりパワーのある部員達とトレーニングに始まって、きつい山行の日々でありました。今考えるととんでもないと思われるのですが、コンクリートブロックをザックに詰め、校舎の1階から4階まで登り降りしたり、4階の壁にザイルをつないで外壁を懸垂下降したり、奥多摩の葛岩でロッククライミングのトレーニングをしたり思い出すことがたくさんあります。山行で一番思い出に残っているのは八ヶ岳の春山です。日大理工山岳部の遭難救助をした思い出。それと60kg位の荷物を背負って裏銀座から槍、その後涸沢に入った非常に苦しい山行の日々。10分歩いてそのまま倒れては5分間いびきをかいてねたという記憶が残っています。冬の志賀高原のスキー合宿ではまだ志賀が今のように開かれていない頃、テント生活をしながらスキーをしました。八ヶ岳の秋、深い唐松の紅葉の落ち葉の中を本当に夢の様な道を歩いた。思い出すときりがないんですが、何か自分の人生の原点になったなあという気持ちが今でも強いのです。
|
高橋さんは長野県エコーバレースキー場で、 「スポーツホテル アンデルマット」 経営の傍ら、 「エコーバレープロスキースクール」の校長をしておられます。 |
第17回 酒井(八尾) 愛子
今お話がありましたように、私は高橋君や男の人達が春の鹿島鑓や八ヶ岳をバリバリやっている一年後に入りました。昨日古い記録を読み返していたら、1年生の歓迎山行はダラダラして非常にまずいので本年はやめるという記録がありました。ああそういえば、初めての合宿は丹沢の大倉尾根から雨の中をしごかれて登ったなあと思い出しました。そういう中に入りまして、女子が非常にお荷物的存在だということが問題になっておりまして、だいぶ議論されましたが、先程のお話を伺ってみますと、女性の方も創部以来頑張っていらした様ですが、それ以上に男性が活躍した後だった為、男女差の問題がクラブの中で問題だったんだと思います。実際の活動はそんな中で、女子が非常に頑張りまして、高橋君達のような猛者達と同じ事を同じ様には出来ないけれど、山が好きだ、やればできるという意見が盛り上がりまして、夏山合宿で裏銀から縦走してきた男子と、上高地から入った女子が横尾で合流して涸沢、穂高を一緒にやるとか、春には男子は八ヶ岳、女子は雲取〜川苔まで縦走するという様な、OBや先生方の支援が強かったとは思いますが、それなりに夏の剣岳に18人もの合宿をしました。そうなると女子も男子もなく、ともかく部を維持していこう、そして目的はどんどん上へいきますので、これもしたいあれもしたいということを、OBから力以上のことをするといわれながらも、皆で頑張ったと思います。
このように、男女差の問題を曖昧のままにしないで真剣に取り組んだ結果、かなり背伸びもあったとは思いますが、夏や秋、春の別パーティーによる合宿やスキー合宿共同合宿など、積雪期を含めて男女一緒のFAC活動というものの一つの基礎ができた、そういう時代だったのではないかと思っております。
女の園で
第22回 中島(井上) 喜代子
私の代は女の子ばかりでした。上級生も心配して下さって、3年生になる頃、男子も1人、2人と増えてきたのですが、ここに出席するのはその時、(山岳部を)つぶさなかった事だけは認めて頂きたいと思います。初めのころは山へいって、下りたらもうやめる、もうやるもんかと思っていて。お嬢さん育ちばかりだったから、山へ行くとご飯も自分で作らなきゃならないし、水も運ばなきゃならないし、何とか1年間終わって、次が今度は男の子ばっかりだったんです。うえのOBが随分心配して下さって、今考えてみれば皆さん裕福なOBではなかったと思うんです。学生さんで。必ず山行には皆さん都合つけて、結局女ばかりの山行でしたから、来て頂いてそれでもったようなものです。女の人が上に立つ今の時代の象徴のような時でした。その点佐治君達は男の子ばかりで、おとなしくて良い子ばかりでしたね。
第23回 佐治 昭
その説明をしますとですね、歴史のなかで女性は救いの神なんですね。我々が1年生で入ってきた時に、女性に見込まれて、山岳部に入らないかといってかなり強引に勧められて、我々はその誘惑に負けて、ぞろぞろと我々男性7人勧誘された訳です。山へ行っても、女性に食事をつくってもらったり、女性の「ガンバッテー」の声に非常に勇気づけられて、その頃やっぱり我々男の子はモテなかったんでしょうね。女性に飢えていたというか、年上の人に憧れをもっていてその結果がこうなったという事だと思います。山岳部にとっては、これは歴史的に救われてのことだったんじゃないかと思います。何故かここに立っているのも、女性、井上さんのおかげだと思っています。楽しい3年間、甘えた3年間を送らせて頂きました。まあ、そんな歴史の一コマでした。
色々な出来事
第25回 金谷 斎
私が丁度25回卒ですが、今日富士高の文化祭に行ってみて余りの寂しさに不安になったんですが、我々の時には非常に人数が多くて、各代に8人位部員がいました。合宿になるとOB、先生を含め30人とか長いパーティーになって、リーダーがストップとか号令をかけても途中に伝令を置かないと伝わらない位でした。こういう時代なんで、山は汚いし、辛いし、若い人は中々入らないと思いますけれど、現役にも頑張ってほしいと思いました。また今は教育委員会とか規制がうるさい様に聞きますが、僕たちがやっていた時代はとても良い時代で、夏山合宿も一週間から10日やらせて頂きました。春山も積雪期も許して頂いてOBの方のサポートの上で、高校生としては中々許して頂けないような春山八ヶ岳とか南アルプスとか行かせて頂きました。こういういい思い出を、現役に味わわせてあげるためにOBの力が必要だと思いますので、私は参加できないんですが、若いOBに頑張って欲しいなあと思います。
第30回 外池 力
私30回ですが、31期に当たる土田(広人)という現役の1年生が東北の飯豊山で熱射病のため遭難死したという富士高山岳部唯一の死亡事故があったのは、丁度私が部長をやっている時でありまして、もう16、7年経っています。そのときOBの方々にご援助頂きまして、特に私が印象に残っているのは、すぐに駆けつけてくれた若いOBの方々、特に田川さんという、今は亡くなってしまった方がいち早く来てくれたことを感謝しているのです。その後中野の古い喫茶店でマカルーに登った大OBも含めまして、今後の富士高山岳部はどうあるべきかということを話し合った会合、この二つが私とOB会を強く結びつけたことでありまして、このことについては大変感謝しております。その後富士高山岳部はそういうOBの力もあり、現役もその後たくさん入ってきまして、第2次、第3次の爛熟期に入りまして、私達の遭難のあと、春山も雪訓も夏山も一週間近くやったように盛り返してきました。そんな訳で、みなさんのおかげをもちまして遭難の事故を乗り越え、こんなことが二度とないよう祈っています。
その後のことですが、亡くなられた土田さんの妹さんも富士高出身で今はお子さんが誕生しまして、ご両親もそれに一生懸命になられているということです。
遭難後皆で何度も訪ねたお寺の住職も今は移られたとのことで、あそこには居りません。プレート(遭難碑)は未だ飯豊の麓に残っていますので、あちらの方に行かれた方はお訪ねください。
<司会>第17回 長谷川 和夫
FACが本当に存亡の危機に陥ったのはその時だったと思います。その時顧問をされていた伊藤先生が真っ青な髭で、憔悴しきった様子で、一生懸命私達に対応を話して下さった姿が忘れられません。本当に当時はご苦労さまでした。それでは続きまして・・・
今日現役山岳部が富士高祭で展示していました。私達今日のスタッフがそこに訪ねて行ったんですけれど、2年生男性2名、1年生女性1名、3年生が2人とか。来年度がちょっと厳しいのではないかと、顧問の先生お二人ともお会いして来たんですけれども、先生がおっしゃるには、今年も夏山合宿に北アルプスに出かけて行ったんですが、会う人は中高年の女性だと(会場爆笑)、だからもう若い人が登らない時期になっていて、この際もう(部が)つぶれても止むを得ないんじゃないかと、つまりもう顧問になり手がいなくなるという話をされ、大変厳しい状況にあると言う話を伺いました。そんなこともありますけれど、FACと現在つながりのある三人に、最近のFACのことを含めてお話を伺いたいと思います。
<次代を担って>
第35回 出岡 学
35期の出岡です。ポスト遭難世代の者です。僕はさっきの遭難があってから5年くらい下に入ったので、僕の代に来てくださっていたOBというのは遭難当時2年生だった方々でした。その頃夏山合宿の前とかに、遭難の話をして下さったり、そういうことを乗り越えて山岳部を建て直していくんだ、という意気込みを感じながらやって来たようにな気がします。そのなかで、細々ですが雪山もやり、夏山も一応成功させ、先輩達の気持ちを引き継いでいました。
第40回 八木 正徳
私が富士高山岳部に入りましたのが、昭和60年という時代で、丁度今出岡先輩が話された外池先輩が大学院を終えられて(OBとして)第一線を退かれた時代でありまして、遭難の印象が薄れた時代で、私が在部する2年前少し人数が減りまして、合宿という形が取れない時代がありました。次の年は人数がやや回復しました。合宿には行けたのですが、北アルプス裏銀座コースの途中で病人が出て3日目に撤退するという形で合宿を終えました。次の年が僕等の代だったんですが、やはり同じコースを計画していながら同じように病人が出まして、その年も撤退しました。つまり3年間合宿が失敗していたという異例な年に僕たちは在部していたわけです。2年の時南ア北部塩見、農鳥、北岳の白根三山を計画しまして、久し振り成功したあと外池さん達先輩が集まって、成功を祝って下さいました。合宿のような大きな計画で不測の事態がいつでも起こりえる山というものの難しさを痛感しました。
その後、部員は増えていったんですが、現代のもやしっ子が増えたんでしょうか、途中病気で倒れたりする者がいたり、活動を各代できないまま、私は高校を卒業しまして、平成に入り大学生になって、平成の山岳部の後輩達と山に行くようになりました。
第43回 中村 精一
僕はこの中で唯一の、未だ大学にも行っていない、進路に迷っている者です。今日は富士高山岳部のよき先輩に色々とこれからの人生について教えて頂こうと思いやって来ました。(人生を間違えるぞ
!!の声あり)見た限りでは結構アウトローな人が多いので(一同爆笑)僕もその道を教えて頂きたく思います。現状は1年生が女子一人だけで、来年の勧誘さえ難しい状態で、僕達も今年勧誘を手伝いましたが、何分校舎も綺麗になって、山という印象が富士高に似つかわしくなくなりまして、後輩達も一生懸命やらなくなっています。打開策というのは難しいと思いますが、一つにはあこがれの(岳)人がだんだん消えていって、僕の頃は植村直巳さんとか、長谷川恒夫さんとかいたんですが、彼らが書く物を読んで山にあこがれて入ってきたというところがあったと思いますし、都会生活と山というものが余りにも離れすぎていて、僕の子供の頃はたまに山に行ったりすることがあり、なじみがあって入りやすかったんですが、今は全く都会と切り離されていて、自然に入る壁を越えるのが難しい。そういう訳で皆さんには(お分かりと思いますが)大学受験を控えて、色々進路を考えるのですが、勉強と山を両立させるのが一番障害となっている部分です。それがうまくやれれば、両立できるということを、皆さん富士高へ来て教えてやって欲しいと思います。
顧問の弁
小泉 千枝
先程一度もうしゃべったので、蛇足を加える必要はないんですが、私名前が小泉ちえだと申しまして、「せんえだ」と書いて普通は「ちえ」なのに蛇足のある人間でございます。それで一つ蛇足を加えさせて頂きます。私が富士高出山岳部と係わったのはOBの方々が何時もご指導くださる山行に、ただ訳も分からないでバテない歩いてついて行けばいいんだという顧問で、ついてまわりまして大変色々な山をご案内頂きまして、今思い出すと丁度40代の10年間でございましたので、50になりました時に、あの大門さん達の北アルプスじゃあない南アルプスの山行に参りまして、ああこれでもうお終いだなあ、ちょっとダメだなあと思いまして止めました。そういう訳で顧問というのはおこがましく、皆様のおかげで山を楽しませて頂いて、今は下から眺めながら、ああ、あそこも行った、あそこも行った、ここも行ったと言って喜んでおります様な人生でございます。どうぞ皆様も地べただけを歩くような人生になった後にもその余生を大いに楽しんで、山で培われた自然や、それから体力や人間関係を大切になさって、良き仲間との良き人生をお続けになりますように祈る次第でございます。ではこれをもって挨拶といたします。